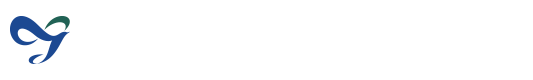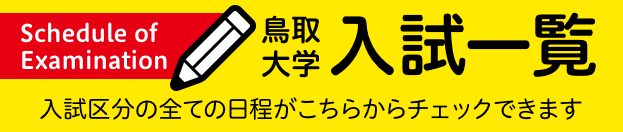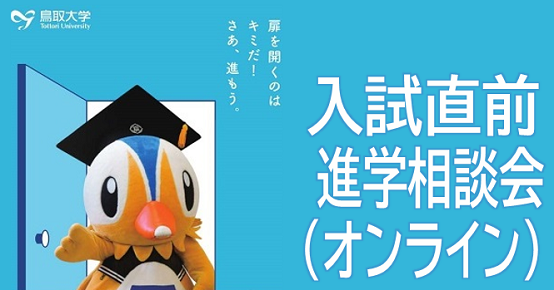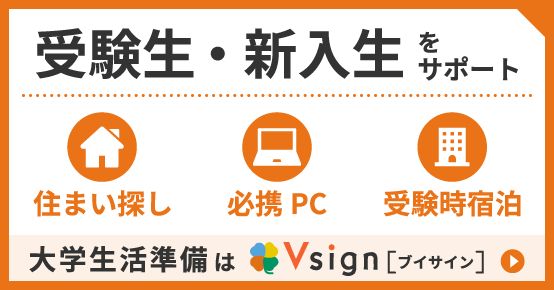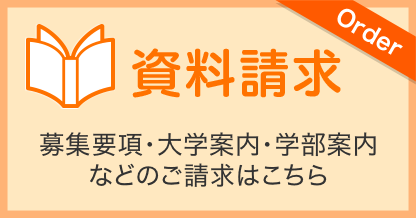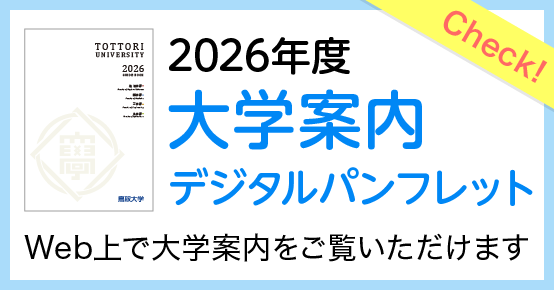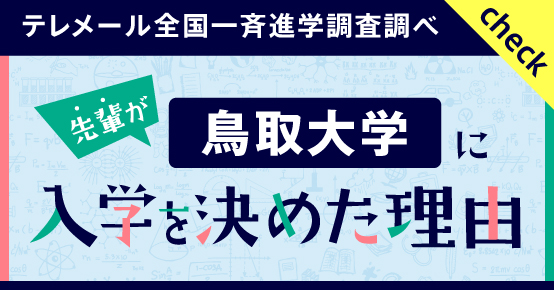2次選考<選考のポイント、面接・論文等の出題例等>2026
面接・論文等の出題例等
- 2025年度総合型選抜Ⅰがどのように行われたかについて、学部・学科・コースの募集単位別にポイントや出題例を示したものです。
- 2026年度総合型選抜Ⅰが下記のように行われるということではありませんので、ご注意ください。
学部・学科・コース
地域学部 地域学科 地域創造コース
全体を通して求める力
自らの地域の発展に貢献できるキーパーソンに成長するための、地域の諸問題への高い関心や行動力、あるいは問題解決に取り組むユニークな発想力とリーダーシップなどが求められます。
- スクーリング
- 講師(1名)が「非営利組織(NPO)は本当に「世の中のためになるのか」?―相違や葛藤に悩む現場からの問い」についての講義(80分)を行い、その後受験者との質疑応答(10分)を行いました。
- 課題論文
- スクーリングの内容に関連した設問(2問)に90分で解答するものでした。設問の内容は、非営利組織はどのような意味で「世の中のためになろうとしているのか」を300字以内で要約するもの(問1)と、あなたが知っている事例、またはこれまで経験してきた事例をあげて、世の中にある「相違」や「葛藤」の解決に向けた取り組みについて600字以内で説明するもの(問2)でした。
- グループ
ディスカッション - 5人ずつ4グループに分かれ、1グループあたり約15分のグループディスカッションを複数回にわたって行いました。テーマは『「相違」や「葛藤」を踏まえたうえで、地域を共に創造する』で、農山漁村や大都市など異なる事情をもつ地域の「相違」や「葛藤」の具体例について意見を出し合いながら、最終的にはそれらを踏まえたうえで、各自がどのように自らの暮らす地域を共に創造できるのかについてグループで議論しました。
- 個人面接
- 提出された「自己推薦書」「調査書」の内容を踏まえながら、地域づくりや地域に関する学びへの主体性を測るとともに、地域学に必要となる知識、思考力等を測る質問をしました。一人当たりの時間は20分程度でした。
選抜方法と求める能力の関連
| 選抜方法 | 知識・技能 | 思考力・判断力 | 表現力 | 主体性・協働性 | 創造性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2次(書類審査) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2次(スクーリング) | ○ | ○ | |||
| 2次(課題論文) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2次(グループディスカッション) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2次(面接) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
地域学部 地域学科 人間形成コース
全体を通して求める力
地域教育のキーパーソンをめざすために必要な、確かな基礎学力、柔軟で創造的な思考力と表現力、他者と協働して問題解決する力を求めます。
- 小論文
- 小論文は2つの問題で構成しました。問題Ⅰでは、大学教育に関する英文を読み、理解する知識および技能をみるとともに、英文から読み取れる二者間の主張を整理しながら、それらを踏まえて自己の考えを述べることで、思考力や表現力をみました。問題Ⅱでは、義務教育における病院訪問教育に関する文章を読み、筆者の議論を踏まえた自己の考えを問うことで、読解力や論理的な思考力をみました。
- 口頭発表
- 口頭発表では、小論文問題Ⅱの解答をもとに、小論文の題材とは異なる状況への応用可否について、自己の意見を求めました。
- グループ
ディスカッション - グループディスカッションでは、朝日新聞記事「子どもの貧困対策法10年『子ども食堂』名付け親が納得できぬこと」を読みながら地域でできることを問いました。子ども食堂の設置箇所数に関するデータも参照しながら、全員で発表の内容や仕方を討議してまとめ、最後に発表しました。
- 個人面接
- 個人面接は、最初に志望理由や卒業後の進路などについて質問し、次に4名の面接官が補足質問を行いました。一人あたりの時間は15分程度でした。
選抜方法と求める能力の関連
| 選抜方法 | 知識・技能 | 思考力・判断力 | 表現力 | 主体性・協働性 |
|---|---|---|---|---|
| 2次(小論文) | ○ | ○ | ○ | |
| 2次(口頭発表) | ○ | ○ | ○ | |
| 2次(グループディスカッション) | ○ | ○ | ○ | |
| 2次(面接) | ○ | ○ | ○ | ○ |
地域学部 地域学科 国際地域文化コース
全体を通して求める力
文化、地域、国際交流など地域と文化に関する分野に関心があり、他者の話によく耳を傾けて理解しようとする姿勢や深く考えを掘り下げる姿勢、それらを分かり易く表現する力を求めます。
- グループ
ディスカッション - 民主主義の課題や意義について記した資料3点(A4版6ページ)を読み、各自で意見をまとめたあとで、多数決による民主的決定について、12名で4時間のグループディスカッションを行いました。司会進行は教員が行いました。
- 課題論文
- 車椅子ユーザーである著者が、テクノロジーの進化とともに、コロナ禍を経て対面の機会が減少しつつある現代社会において、他者と直接会う「対面」による相互作用の価値について述べた文章(A4版3ページ)を読み、90分で2問の設問に解答するものでした。設問の内容は、筆者が提示した他者と対面することの意味の要約(200字以内)と、他者との関係構築をどのように捉えるのか、受験生自身の言葉で論じるもの(800字以内)でした。
- 個人面接
- 3名の面接官による、一人あたり15分の面接を行いました。
選抜方法と求める能力の関連
| 選抜方法 | 知識・技能 | 思考力・判断力 | 表現力 | 主体性・協働性 | 創造性 | 思考の柔軟性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次(グループディスカッション) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2次(課題論文) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2次(面接) | ○ | ○ | ○ | ○ |
農学部 生命環境農学科
全体を通して求める力
生命環境農学科では、自ら積極的に学び、傾聴力と協調性を持って学んだことを実践で応用できることを重視しています。高校時代に履修できる、あらゆる科目を積極的に学び、知力、体力、コミュニケーション力、気力、実践力の基礎を養ってください。
- 課題論文
- 「あなたの達成したい「夢」は何ですか?その「夢」を実現するために,鳥取大学農学部が最適な学びの場であると考える理由と,入学後に意識して取り組みたいことは何かを1,000字程度で述べてください。」という課題について記述するものでした。
- グループ
ディスカッション - 「日本では第一次産業の担い手不足が大きな問題となっています。これを解消するためにはどうすればよいか、農学という観点から複数のアイデアを出し合い、それらを検討して最終的にひとつにまとめてください。」というテーマについて、グループディスカッションを行いました。
- 個人面接
- 3名の面接官による、1人あたり25分の面接を行いました。また、基礎的な英語についても試問しました。
選抜方法と求める能力の関連
| 選抜方法 | 思考力・判断力 | 表現力 | 主体性 | 協働性 | 農学の課題解決に対する意欲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2次(課題論文・面接) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 2次(グループディスカッション) | ○ | ◎ |